今回は 浪人の4月 に取り組むべきことの1つ目
「生活をルーティーン化することの大切さ、ルーティーン化のやり方」をお伝えさせていただきます。
これで今後の成績の伸びが変わると言っても過言ではないくらい大切なこと。
覚悟を持って読んでほしいと思います。
なぜ「ルーティン」が大切なのか
私は、浪人において最も重要なことは「自己管理」であると思うんですよね。
現役時代に上手くいかなかった人は、この「自己管理」がうまくいかなかった人が多いと思います。
では、受験における「自己管理」とは、一体何でしょうか?
それは「継続的に勉強を続けるためのスケジュール管理」のことです。
徹底したスケジュール管理をするとどんなメリットがあるのでしょうか。
それは・・・
・勉強時間にばらつきが出ない
・勉強を習慣化できる
・勉強の習慣化によって勉強が苦ではなくなる
・次に何を勉強しようかと考える時間をなくせて勉強の効率が上がる
などといった効果があります。
私が浪人でうまくいき、現役ではMARCH全落ちだったにも関わらず、浪人で早慶複数学部に合格することが出来た理由の1つに、きちんとスケジュール作成をしたことがあると思います。
スケジュール管理を徹底して、それ淡々とこなす。
これが大事です。
考えてみてください。浪人生は1年中勉強するんですよ。
現役生は定期テストがあったり、体育祭があったりでメリハリをつける大きな行事がある。
でも浪人生にはそれがない。
そんな状況で勉強を続けられる状態にするか。
それは習慣化するしかないんです。
大人を見てみてください。
ちゃんと毎日同じ時間に起きて、同じ時間に出社していますよね?
その理由は何ですか?
答えは明確です。
それが習慣になっているから。そうするのが普通だから。
高校生がしっかり1時間目の授業にほぼ全員が遅刻せずにこれるのはなぜですか?
これも同じです。
それが習慣になっているから。それが普通だから。
高校生の登校時間レベルでこんなことできるのに、浪人生の勉強の話になると急にこれができなくなる。
なんででしょうね?
でも、大切なものだと思います。
浪人してしまったからにはルーティーン化を徹底しましょう。
ちなみに河合塾の講師で、TOEICの参考書などで有名な森田哲也先生もルーティンの重要性を説かれていました。
5分35秒くらいからお話しています。
ルーティーンの作り方
それでは実際に、どうルーティーン化していくかどのようにスケジュールを作成するかお伝えします。
まじで完全保存版です。
一学期も、夏も、二学期も、冬もやり方は同じです。
代ゼミの佐藤幸夫講師が最高の動画を載せてくれていたので、それを視聴してからこちらのブログを読むと、理解が深まると思います。
予備校の時間割が決定する
この段階ではやることはありません。
どこに空き時間があるかをなんとなく認識してください。
予備校の時間割の組み方についてアドバイスするならば、受けたい先生をなるべく受けることと、ある特定の日に授業が集中することを避けるべきってことですかね。
空き時間にやることを埋めていく

月曜日と火曜日分しか入れていませんが、これが一例です。
毎日この時間にこれをやるということを決めていってください。
・授業は予習の新鮮な状態で臨みたいので予習は授業の前日か当日
・復習は早めにしたいので授業の当日か翌日
この二つをまずは意識すると、うまくスケジュールが作れると思います。
行き帰りの通学時間が短い人は、単語の学習などもこのスケジュール表に書き込みましょう。
徹底的に書き込みましょう。
苦手教科には多く時間をとっておくなんてのもありだと思います。
加えて、必ず調整時間を加えるようにしましょう。
週によっては、とても授業の内容が多かったなんて日もあるとおもいます。
時間通りにやりきれなかったことを想定して調整時間をとりましょう。
あと、最初のうちは余裕をもってスケジュールを作りましょう。
実際にこなしてみる
スケジュールを作成したら、実際にその通り過ごしてみましょう。
すると
「この授業の予習は1時間もいらないな」「この復習はもっと時間欲しいな」
なんて思いが出てくると思います。
そうしましたら、スケジュールを修正しましょう。
最初の1か月はスケジュールの修正をしながら試行錯誤していくのが大事です。
そうしていくうちに、自分だけの最高の時間割が完成します。
そうなると勉強時間が増えます。
やるべきことをやれている実感を得ることが出来ます。
勉強がルーティーン化します。
⇒成績が上がります。
浪人の4月 にやるべきこと まとめ
浪人において最も重要なことは、「自己管理」であるとお伝えしました。
「自己管理」=「勉強時間の管理」を実際に見える化して勉強の流れをつかみましょう。4月に絶対やるべきですよ!!浪人生だけではなく、現役生だとしてもやってみるべきです。
では、また。応援しています。頑張ってください。
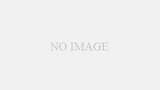
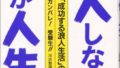
コメント
[…] […]